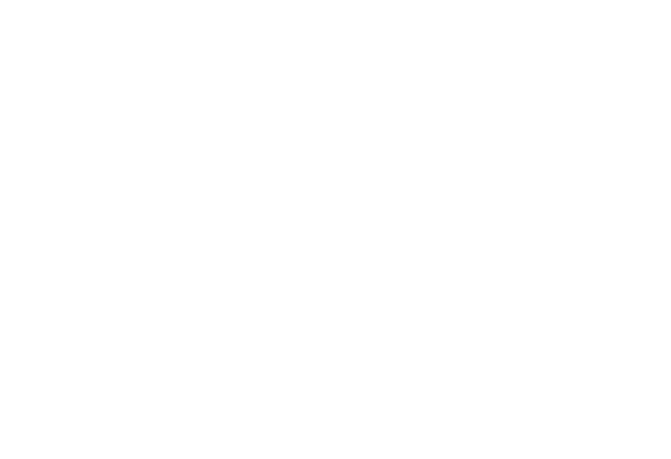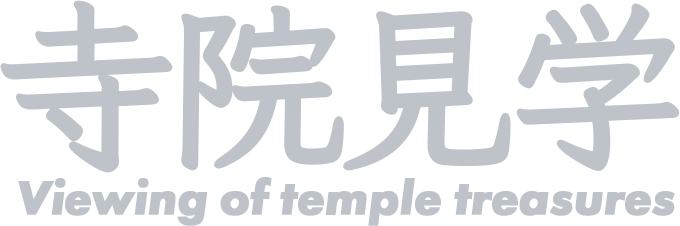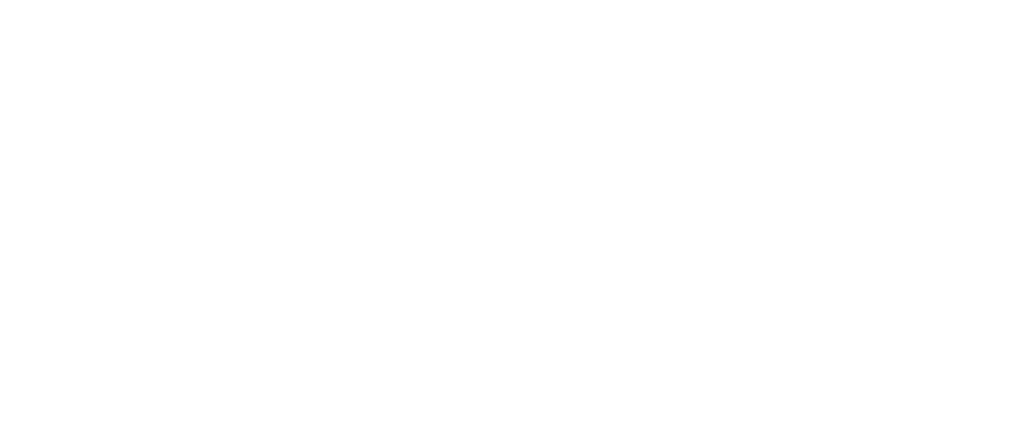
宿坊、ランチのご予約・予約変更、キャンセルはこちら
-
星供養のご報告
毎年、真言宗の寺院で行われる「星供養」。清浄心院では2月3日に星曼荼羅(ほしまんだら)を掲げた儀式を執行。囲炉裏の間(土室)では僧侶が読経する儀式に宿泊者も参列しました。当日の模様をご報告いたします。 -
春の寺宝展を開催!
3月から春の寺宝展示会は南紀男山焼の花生(花瓶)です。南紀男山焼は紀州藩10代藩主・徳川治宝が藩の御用窯として開かせたのが起源。ぜひ、この会期中にご覧ください。 -
春彼岸護摩供養のご案内
清浄心院では3月19日から3日間、春彼岸供養の護摩行を執り行います。清浄心院鳳凰奏殿にて池口恵観住職が仏様ご先祖様や、亡き大切なご家族様のお塔婆を立てて、護摩供養いたします。また、仏様ご先祖様にたくさんのご供物をお供えします -
【恵觀住職】3月のスケジュール
鳳凰奏殿にて期間中は毎日12時前後より護摩行を開始いたします。どなたでもご参加いただけますので、お気軽にお詣りください。また期間中は14時30分頃から恵觀住職のご相談・お加持があります。 -
田原総一朗&池口惠觀 書籍発売!
2月3日に田原総一朗氏×池口惠觀住職の対談本『闘う二人 祈りとジャーナリズム』(セルバ出版)が発売されました。「祈り」と「ジャーナリズム」、それぞれの道で闘い続け、40年以上の付き合いとなる二人による新書籍です。 -
TV番組『おはよう朝日』で紹介
2月12日(木)AM5:00〜8:00放送のテレビ番組『おはよう朝日』(朝日放送テレビ/関西ローカル)にて、清浄心院の護摩行体験と精進料理、精進カレーなどを取材していただきました。視聴可能な方はぜひご覧ください。

恵観法主は、室町時代から500年以上続く真言密教修験の第十八代目の相承者・薩摩の国の傳燈法師であり、相承秘伝の護摩を日々厳修、一切衆生の祈願に応えられています。また、真言密教最高秘法「焼八千枚護摩供」を101回以上も修法。その絶大な法力は不世出の大行者として、広く内外に知られています。
昭和63年12月には真言密教最高厳儀「学修潅頂」に入壇受法。傳燈大阿闍梨位にご昇供されました。平成元年には100日間にわたり、密教史上誰もなしえなかった秘法「100万枚護摩行」を修法。1日に乳木1万本と添え護摩木3千枚を焚焼するという壮絶極まりない決死の行を無魔成満されました。平成26年、高野山別格本山・清浄心院住職に就任。
高野山 別格本山 清浄心院
〒648-0211
和歌山県伊都郡高野町高野山566番地
TEL 0736-56-2006(代)
営業時間:9:00-17:00
年中無休
当院へのお問い合わせは、お電話にて承ります。